認知症の栄養療法の前に・・・ 「認知症対策は食事から」日本認知症ネットワーク
- 奥平智之

- 2020年6月9日
- 読了時間: 3分

高齢者は胃腸の機能が低下し、食べる量が減ることから、十分な栄養素を摂ることができずに、
「栄養型うつ」になることがあります。
栄養型うつとは、栄養の問題に起因するメンタル不調のことです。
また、高齢者は、低栄養により便秘や筋力低下、免疫力が低下している方が多いです。
認知症に栄養療法を行う前に、基本的なところをまとめておきたいと思います。
①認知症の血液データは、脱水傾向や軽い溶血で、全体的に数値が高めに出ていないか注意。《血液栄養解析》
タンパク質代謝が低下して、脱水傾向で、総タンパクやアルブミン、ヘモグロビンなどの検査数値が見かけ上高くなっていることがあります。
筋肉のけいれん、口渇、めまいなどは、初期の軽い脱水傾向の症状です。
また、低栄養で細胞の膜がぜい弱で、些細なストレスで血球の膜が破けて、軽い溶血(膜障害)がみられることが多いです。アルブミン、尿素窒素BUN、亜鉛、鉄、フェリチン、など、大切な項目が高めの数値になっていることがあります。
②認知症のタイプでも低栄養の頻度が一番多いのは、レビー小体型認知症。
Roque, M., Salva, A., & Vellas, B. (2013). Malnutrition in community-dwelling adults with dementia (NutriAlz Trial). The journal of nutrition, health & aging, 17(4), 295-299.
薬剤やサプリメントの過敏な方が多いので、ご家族にきちんと説明したうえで、少量から慎重に投与することが大切です。
抑うつ傾向であることが、アルツハイマー型認知症よりも多いです。
便秘、嗅覚障害が多いのも、レビー小体型認知症の特徴です。
③偏食が多いのは、前頭側頭型認知症(ピック病)。
こだわりが強く、偏食が多いです。
行動を止めようとすると混乱したり、興奮し、怒ることがあります。過食、テーブルマナーの逸脱がみられることも多いです。
ピックは、一番、介護が大変な認知症のタイプです。
④「食べ忘れ」 、「食事中の注意散漫」が、低栄養の原因になることがある。
食事を用意しても、なかなか食事を食べ始めない、もしくは、口を開けない場合は、はじめの一口をだけ、スプーンなどで介助して食べてもらいましょう。
そうすることで、食べ物であること、食事を開始する時間であることがわかります。
それから、スプーンやお箸を手渡して一人で食べてもらうのがいいです。
テレビや周囲の人が気が散って食事が摂れない場合は、テレビを消したりするなど、静かな環境を整えましょう。
食事の途中でトイレに行くと、食事から気持ちが離れてしまいます。食事の前にトイレを済ませておきます。
⑤十分量食べれなくて、カロリー不足になりそうな時は、食事に「良質な脂質」を足す。
脂質は少ない量で高カロリーなので上手に活用しましょう。
アマニ油、えごま油、オリーブオイル、ココナッツオイルなどをお料理に加えます。
⑥食事したことを忘れていても、叱らない
食事を終えたのに「まだ食べていない」と言う。⇒「今食べたばかりでしょ!」ではなく、「はい。今から、食事の準備をしますね。」と言ってから、他の話題に持っていく。
もしくは、お茶やおやつを用意して「これを食べて待っていてください」と付け加えるのも良いでしょう。
食べたことを説得しようとしても無駄で、説得することが、被害感情、不安感、怒りにつながります。
「認知症対策は食事から」です。
「血液栄養解析を活用! うつぬけ食事術」https://amzn.to/2uv1wju
日本認知症ネットワーク 奥平 智之

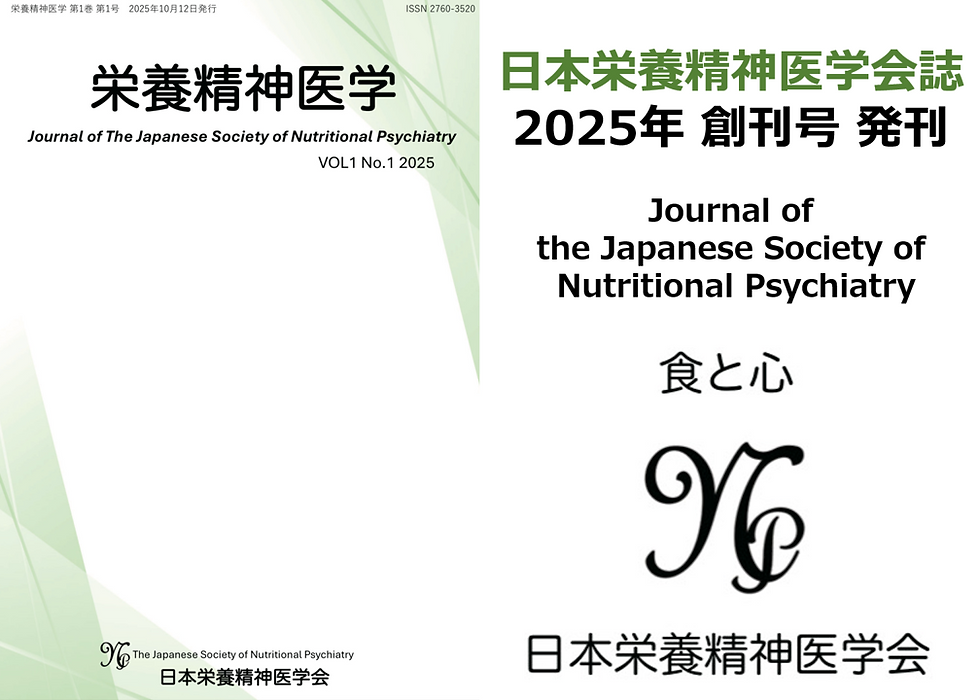


コメント