キヌレニン経路と神経精神疾患:単純化できない分岐点【栄養精神医学の重要性】
- 奥平智之

- 2025年8月5日
- 読了時間: 3分
トリプトファン代謝の大部分(約95%)を占めるキヌレニン経路(KP)。
この経路は決して一本道ではなく、神経系に対して相反する作用を持つ2つの分岐点を形成しています。
🔵 キヌレン酸(KYNA)ルート
・NMDA受容体の非競合的アンタゴニスト
・KYNAの過剰産生は、グルタミン酸伝達を抑制し、
→ 統合失調症の認知機能障害や陰性症状に関与
🔴 キノリン酸(QA)ルート
・NMDA受容体のアゴニストであり、強い神経毒性を持つ
・QAの蓄積は、
→ うつ病・神経変性・炎症性脳障害との関連が多数報告
このKYNAとQAのバランスの破綻(代謝の偏位)こそが、
統合失調症やうつ病など、異なる神経精神疾患の病態を分ける鍵であると考えられています。
つまり:
✔ KYNA優位 → NMDA遮断 → 統合失調症の陰性症状・認知障害
✔ QA優位 → NMDA過剰興奮 → うつ・神経毒性・炎症性脳障害
🧠 この視点を持つことで、「グルタミン酸仮説」の臨床応用や、
栄養・代謝からの介入戦略(例:ナイアシン補充・炎症制御)も新たな地平が見えてきます。
ちなみに、
✅ 周辺血で測定できるキヌレニン/トリプトファン比やキヌレン酸/キノリン酸比は、代謝状態の目安として注目されていますが、中枢(脳内)代謝を直接反映するものではない点には留意が必要です。
【KYNA/Q A比とは?】
トリプトファンが代謝されるキヌレニン経路における、
「神経保護性 vs 神経毒性」のバランスを評価する指標です。
✅ 栄養不足、慢性ストレスや炎症は、IDO活性を上昇させ、キヌレニン経路を偏位させる一因になります。
臨床応用の可能性
グリシン部位作動薬(D-セリンなど):NMDA受容体を正に調節
炎症抑制やナイアシン補充:キヌレニン代謝の偏位是正
NMDA機能を正しく調整する新規抗精神病薬の開発が進行中
・Morris G, et al. (2021). The kynurenine pathway in schizophrenia: Molecular mechanisms and therapeutic implications. J Affect Disord.
・Savitz J, et al. (2020). The kynurenine pathway and neuropsychiatric disorders: Mechanistic insights and therapeutic opportunities. Neuropharmacology.
・Badawy AAB. (2017). Kynurenine Pathway of Tryptophan Metabolism: Regulatory and Functional Aspects. Int J Tryptophan Res.
・Chen W, et al. (2022). Niacin deficiency and altered NAD metabolism in schizophrenia. Front Neurosci.
#メンタルヘルスは食事から #栄養精神医学 #統合失調症 #うつ病 #キヌレニン経路 #NMDA受容体 #キノリン酸 #キヌレン酸 #精神科専門医 #奥平智之 #日本栄養精神医学研究会 #食事栄養療法倶楽部
9/17【耳・鼻・のど】耳鼻科の不調に役立つ!【栄養と漢方のWEB】<アーカイブあり>
10/12【祭】メンタルヘルスは食事から(日本栄養精神医学医学研究会2025年総会)
✳︎今後の予定は、奥平智之ホームページ のスケジュールもしくは、日本栄養精神医学研究会のスケジュールにより詳しく記載


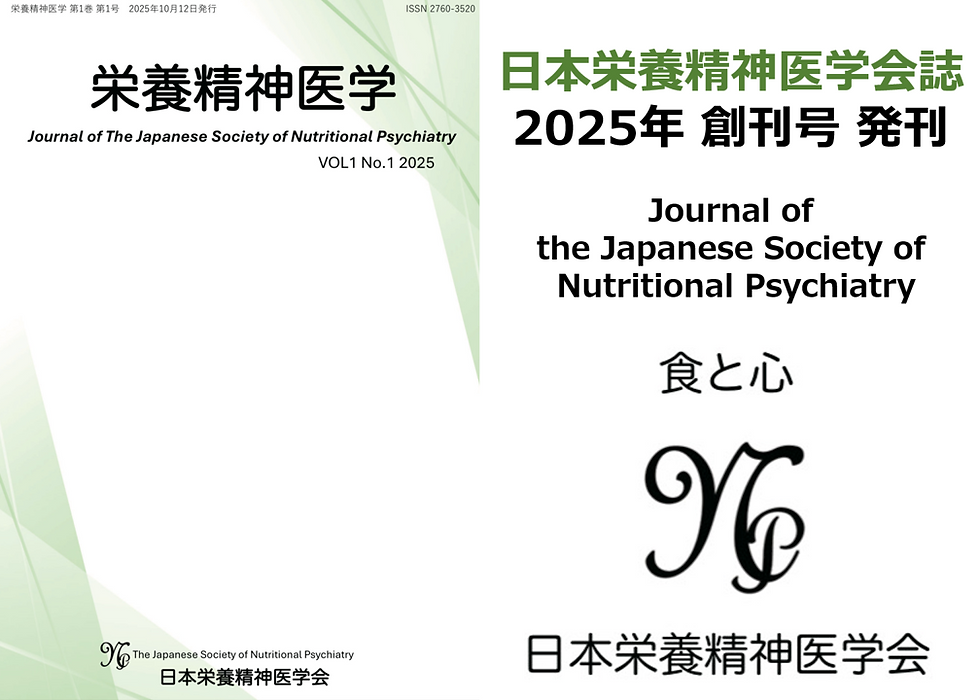


コメント