栄養医学的治療の土台~胃腸を整える方法~
- 奥平智之

- 2020年3月9日
- 読了時間: 2分
更新日:2020年3月16日

栄養医学的な治療のベースは「胃腸」を整えることです。
腸の不調はありませんか?
便秘や下痢、腹部膨満感や腹痛、食べ物に過敏症、便のにおいがきつい、便の形がバナナ状でないなど・・・
腸の状態によって優先順位ややるべきことは変わりますが、基本的に気をつけるべきことは同じです。できることからやってみましょう。
消化不良は、腸の不調の原因になります。
胃部不快感、胸やけ、制酸剤の常用、咀嚼回数が少ないなどは要注意。唾液や胃酸の分泌を促すために、酸味のあるものを意識してみましょう。例えば、レモン、梅干し、酢、ゆず、すだちなど。消化を助けるには大根おろしなどを食事に添えるのも〇。ボーンブロスも〇。
腸の粘膜に大切なビタミンDや亜鉛は、不足している人が多いので要注意。腸の細胞のエネルギー源となるグルタミンも下痢や軟便の方によく使われます。グルタミンは、ストレスや運動などにより需要が高まり、免疫にも関与しています。
胃腸を整えるには、生薬や漢方も活用すると良いでしょう。例えば、生薬に含まれる黄連や黄柏に含まれるベルベリンは、抗炎症効果が期待できます。漢方薬では黄連解毒湯などがありますが、胃炎などに使われることがあります。
有害菌が有意な人は、いろいろ試して自分にあった有用菌(乳酸菌やビフィズス菌など)を継続的に多めに摂取しておくとよいでしょう。
水溶性食物繊維は、腸内細菌によって大腸の細胞のエネルギー源となる短鎖脂肪酸に変わります。短鎖脂肪酸は、腸内を弱酸性にして有害菌を抑え、有用菌を増やし、肥満を抑える効果も期待できます。
不溶性食物繊維は、水分を吸収して便を増量し、排便を促す効果があります。また、農薬や食品添加物、重金属、化学物質などの有害物を吸着し排泄する働きもあります(鉄欠乏女子テケジョ救出ガイドp68)。
腸の不調の背景に、カンジダの異常繁殖があります。カンジダは、単糖類や二糖類がエサになります。甘い物がやめられない人は要注意。
また、慢性的に腹部膨満感がある人は、SIBO(しーぼ:小腸に菌が異常増殖した状態)が背景にある可能性があります。消化力をあげて未消化物を減らすことと、まずは、パンなどの小麦を控えたり、発酵性の糖質を控えてみましょう。少量のクローブやガーリック、オレガノ、カルダモン、オリーブ葉などを取り入れてみるのも良いでしょう。



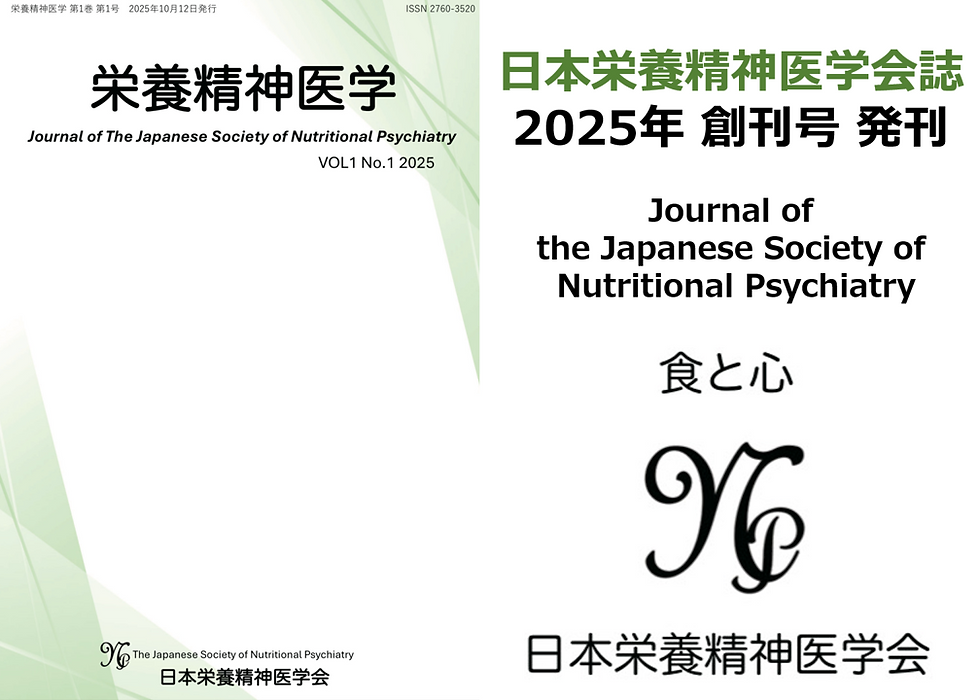


コメント