top of page

【食と心】栄養精神医学
メンタルヘルスは食事から

検索


抗菌ハーブを活用しよう:SIBO対策・風邪予防に/ 小腸内細菌の異常増殖には、低FODMAP(フォドマップ)療法
腹部膨満感、ガスが多い、便秘、下痢、腹痛、悪心、倦怠感、肌トラブルなどの症状がある人はいませんか? 便秘や下痢を繰り返す過敏性腸症候群の背景にはSIBO(小腸内細菌の異常増殖)があることが多いです。抗菌ハーブを活用してみましょう。

奥平智之
2020年6月15日読了時間: 4分


クローブの8つの特徴:奥平式クローブ水:抗菌・抗酸化・鎮痛、クローブ茶、抗菌ハーブ水、マグネシウム補充がポイント
「奥平式クローブ水」の作り方:夏のペットボトルのお水も衛生的に+不足しやすいマグネシウム補給 ➡ 水500ml+クローブ3つ+にがり数摘
★「奥平式クローブマウスウォッシュ」:クローブでうがい
前夜に「100mlの水」にクローブを3つ+にがりを数摘を入れておく。

奥平智之
2020年6月11日読了時間: 4分


【「感染対策」は「栄養」による免疫力の向上から】
5つの大切な栄養素をCOVID-19 コロナウイルス対策として今回取り上げます。「感染対策」は「栄養」による免疫力の向上からです。

奥平智之
2020年4月13日読了時間: 2分


急性ウイルス性呼吸器感染症の発症リスクを抑えるビタミンD血中濃度は?
ビタミンDと言えば、「鮭」、青魚(いわし、さんま、あじなど)、かれい(まがれいなど)、うなぎ、きのこ類(干ししいたけ、きくらげなど)、卵など・・・ですが、

奥平智之
2020年3月16日読了時間: 2分


腸管に対する亜鉛欠乏の影響は?
健康な腸には、亜鉛が欠かせません。足りないと免疫力も低下してしまします。亜鉛と言えば、牡蠣、牛肉、卵、納豆、レバーなど・・・

奥平智之
2020年3月12日読了時間: 2分


【どうする?腸ケア】腸のカンジダ対策の一助に奥平式クローブ水
栄養医学的治療に大切な腸ケア。腸においてカンジダの異常繁殖がみられる人は、クローブを日常生活に取り入れてみましょう。実験では、・・・

奥平智之
2020年3月11日読了時間: 2分


栄養医学的治療の土台~胃腸を整える方法~
まず、胃腸を整えるためにやるべきことは・・・・

奥平智之
2020年3月9日読了時間: 2分


【感染対策:奥平式クローブ水】パート3 マグネシウム&ビタミンD
コロナ感染予防。作り方は、簡単。お水500ml+クローブ1~5個+にがり数滴。これに、オレンジなどの柑橘類、シナモンを入れると、胃腸にもよく、美味しい。不足しやすいマグネシウムは、粘膜に大切なビタミンDをサポート。是非、コスパのいい感染対策、奥平式クローブ水を活用を。

奥平智之
2020年2月28日読了時間: 3分


【①感染対策②浄め③カンジダ対策としての「クローブ」】奥平式クローブ水
コロナなどの感染予防としては、「ペットボトルの水500ml+乾燥したクローブ3つ+にがり数滴」(奥平式クローブ水)をこまめに少しずつ飲んだり、うがいしたりしています。

奥平智之
2020年2月20日読了時間: 2分


鉄欠乏の子ども(テケコ)~鉄欠乏の影響~
子どもの鉄欠乏の影響は?

奥平智之
2020年1月30日読了時間: 2分


鉄の吸収に影響する要因は?
鉄の吸収率は何に影響されるのかもう一度確認しておきましょう。

奥平智之
2020年1月7日読了時間: 1分


「栄養型うつ」とは?
「栄養型うつ」とは、栄養の問題に起因するうつ状態です。

奥平智之
2019年10月28日読了時間: 1分


大人の発達障害と精神疾患の見分け方
【大人の発達障害と精神疾患の見分け方】 大人においてASD、ADHDを診断する際に大切なことは、「発達歴」「経過」。 幼少期から特徴的な症状があり、成人になるまで連続性があること。 他の精神疾患では、発症時期の急な変化を見いだせることが多い。...

奥平智之
2019年7月16日読了時間: 2分


「亜鉛」足りている?ミネラルはバランス!:血液検査の重要性:亜鉛欠乏・低亜鉛血症
ミネラルの摂取はバランスが大切です。 血清亜鉛は、いろんな因子に影響されますが、概ね『100μg/dl』を目指して摂取してほしい重要ミネラルです。 亜鉛を補充する際は、血清銅も亜鉛も、どちらも100μg/dl程度に。
低すぎず、高すぎず、2つの数字のバランスを確認します。

奥平智之
2019年5月21日読了時間: 2分
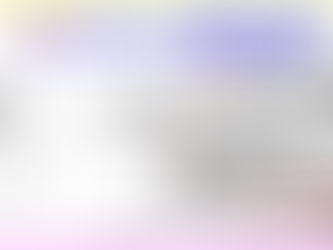

リーキーガット(腸漏れ)症候群とゾヌリンの仕組み
リーキーガットという言葉は、Leaky (漏れている)Gut(腸)という意味で、Increased Intestinal Permeability(腸管壁浸漏症候群)とも言います。 これは、小腸粘膜の細胞と細胞の間のタイト・ジャンクション(密着結合)が緩んでくる状態です。

奥平智之
2019年5月20日読了時間: 2分



奥平智之
2019年5月16日読了時間: 1分


食べたタンパク質が機能的な役割を果たすために:カロリー不足では摂取したタンパク質が本来の役割を果たせない
つまり、せっかく摂ったタンパク質も有効に使えないのです。
タンパク質が、単に『エネルギー源』として、『消費』に回されてしまうからです。
カロリー不足だと、筋肉も分解されてエネルギー消費に動員されてしましまいます。筋肉が減ると血糖調節も不利になります。
胃腸が弱く食べれない人は、ま

奥平智之
2019年3月28日読了時間: 2分


栄養精神医学におけるレジリエンスとは?ストレス耐性(予防力)+自己治癒力(回復力)
精神医学においてレジリエンス(resilience)に決まった訳語はないが、筆者のレジリエンスの定義は「ストレス耐性+自己治癒力」である。レジリエンスは、元々ストレスと同じく物理学の用語で、ストレスは外力による歪みを意味し、レジリエンスはその外力による歪みを跳ね返す力として使われ

奥平智之
2018年5月25日読了時間: 2分


栄養精神医学(Nutrition psychiatry)とは?
栄養精神医学(Nutrition psychiatry)とは?精神症状・身体症状・向精神薬に対する食事・栄養・腸管の影響を考える精神医学の一分野です。栄養精神医学は、食事や栄養の観点から患者さんのレジリエンス(ストレス耐性+自己治癒力)の向上に貢献すること期待される分野といえます

奥平智之
2018年5月15日読了時間: 2分
bottom of page

